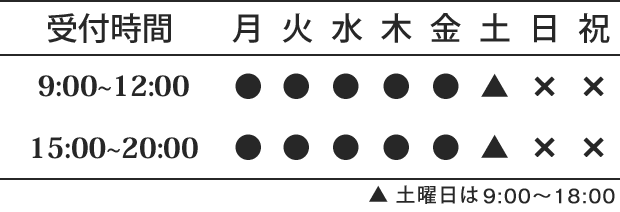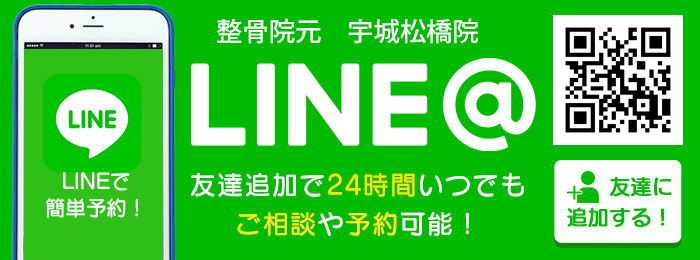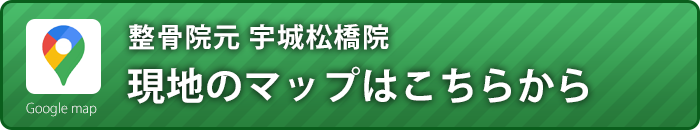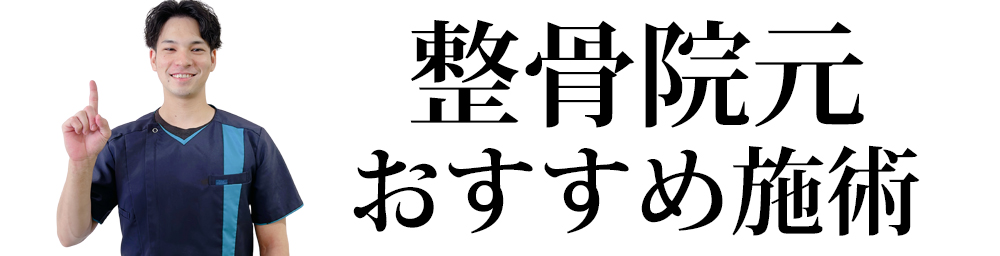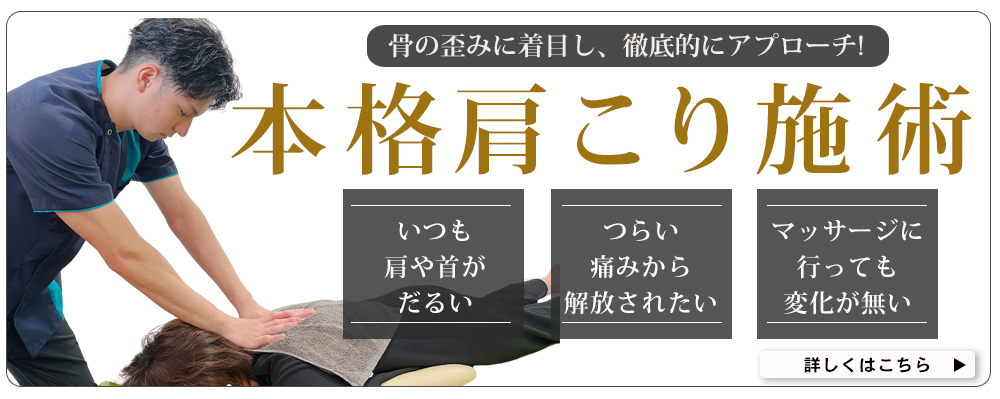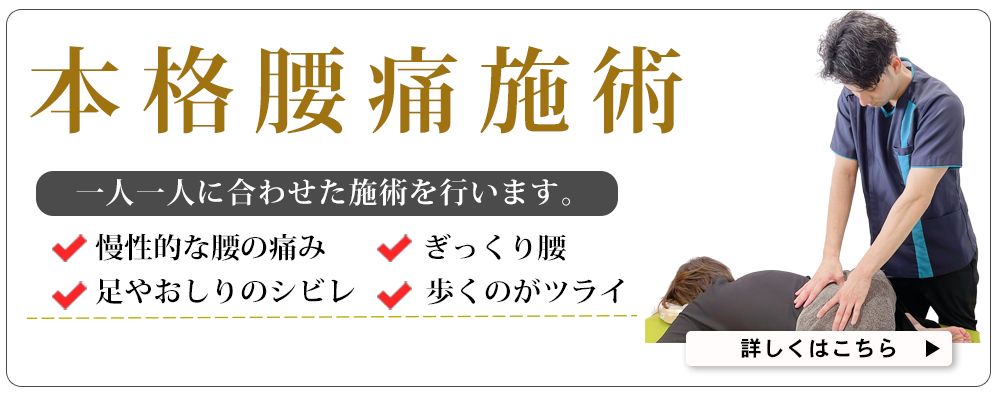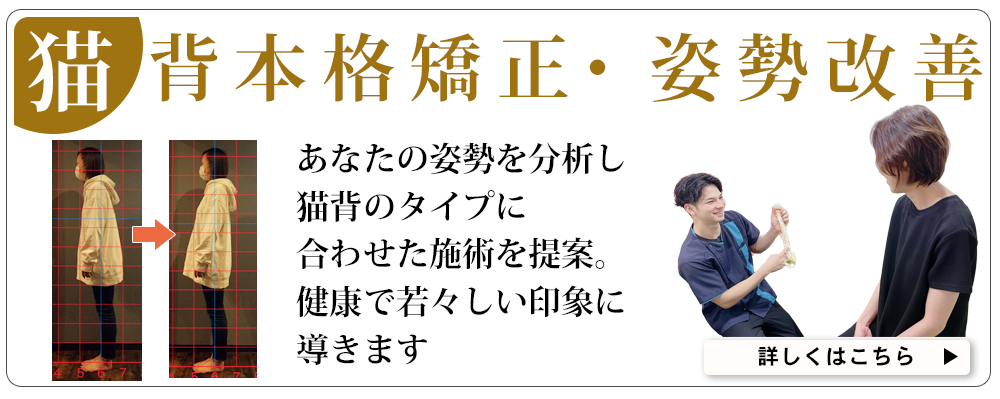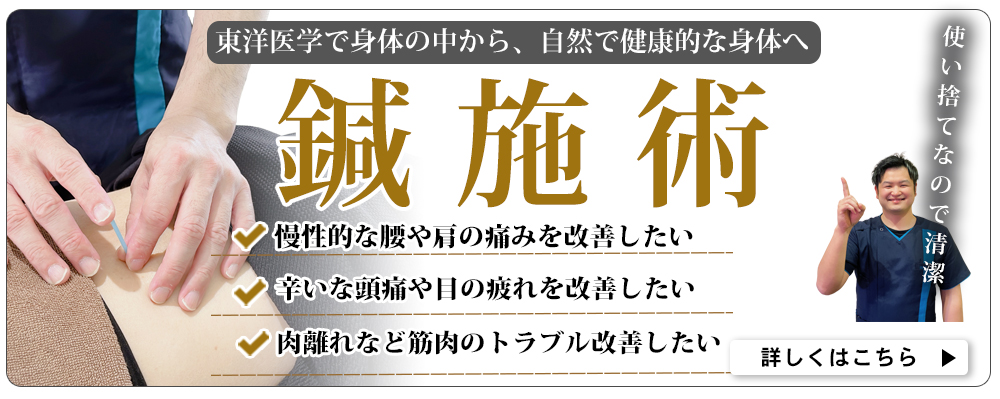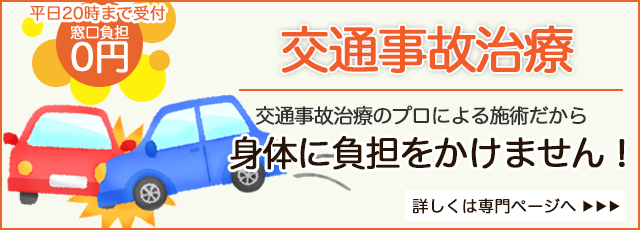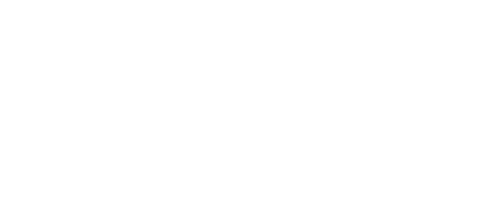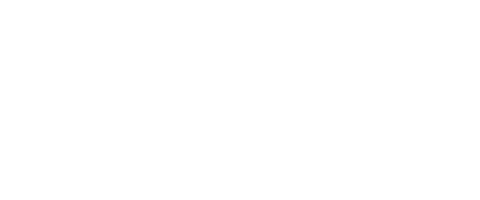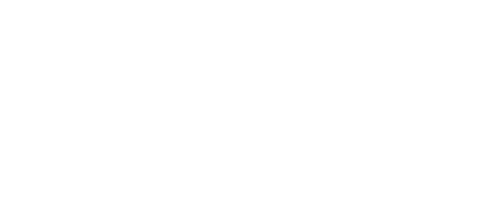首から肩にかけて固くなりやすい筋肉の解説
肩こりは多くの人が悩む問題です。特に首から肩にかけての筋肉が固くなることで、肩こりが引き起こされることが多いです。ここでは、肩こりを引き起こしやすい筋肉について詳しく解説し、それぞれの筋肉がどのように肩こりに関与しているかを説明します。
僧帽筋(そうぼうきん)
僧帽筋は、首の後ろから肩甲骨、さらに背中の上部に広がる大きな筋肉です。この筋肉は、肩の動きをサポートする重要な役割を担っています。しかし、長時間のデスクワークやスマートフォンの使用などで同じ姿勢を続けると、この筋肉が緊張しやすくなります。僧帽筋が緊張すると、首や肩に痛みやこりが生じ、肩こりの主な原因となります。
肩甲挙筋(けんこうきょきん)
肩甲挙筋は、首の側面から肩甲骨にかけて伸びる筋肉です。この筋肉は、肩甲骨を持ち上げる動きを助けます。肩甲挙筋が緊張すると、肩甲骨の動きが制限され、肩こりや首のこりを引き起こす原因となります。また、この筋肉はストレスや疲労がたまると特に硬くなりやすい特徴があります。
大菱形筋(だいりょうけいきん)・小菱形筋(しょうりょうけいきん)
大菱形筋と小菱形筋は、背中の上部に位置し、肩甲骨を背骨に引き寄せる役割を持っています。これらの筋肉が緊張すると、肩甲骨が固まり、肩や首の動きが制限されます。結果として、肩こりの症状が悪化することがあります。
胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)
胸鎖乳突筋は、首の前側から鎖骨にかけて伸びる筋肉で、首を回したり、前後に動かしたりする際に重要な役割を果たします。デスクワークなどで前傾姿勢が続くと、この筋肉が緊張しやすくなります。胸鎖乳突筋が緊張すると、首や肩に負担がかかり、肩こりや首のこりが生じやすくなります。
前鋸筋(ぜんきょきん)
前鋸筋は、脇の下から肩甲骨にかけて伸びる筋肉です。この筋肉は、肩甲骨を安定させる役割を持ちます。前鋸筋が緊張すると、肩甲骨の動きが制限され、肩や首に不快感を感じることがあります。この筋肉の緊張も肩こりの一因となります。
肩こりを防ぐための日常の工夫
肩こりを防ぐためには、日常生活での姿勢や動きを意識することが大切です。まず、デスクワーク中の姿勢を正すことが重要です。背筋を伸ばし、肩をリラックスさせ、目線を水平に保つよう心がけましょう。また、定期的にストレッチを行い、筋肉の緊張をほぐすことも効果的です。
適度な運動も肩こりの予防に役立ちます。特に、背中や肩周りの筋肉を強化する運動は、姿勢を改善し、肩こりの発生を防ぐ効果があります。ヨガやピラティスなどの柔軟性を高める運動もおすすめです。
肩こりがひどくなる前に、早めに対策を取ることが大切です。専門家のアドバイスを受けることも有効です。「整骨院元宇城松橋院」では、肩こりに関する専門的な知識と技術を持ったプロの柔道整復師が、個々の症状に合わせたアドバイスを行っています。肩こりに悩んでいる方は、ぜひ一度ご相談ください。
肩こりは日常生活の質を低下させる厄介な問題ですが、適切な対策を取ることで予防・改善が可能です。日常生活でのちょっとした工夫や専門家のサポートを活用し、健康的な生活を送りましょう。